法定検査
■簡易専用水道検査
「水道法第34条の2第2項に基づく簡易専用水道の管理についての検査」
(国土交通大臣・環境大臣登録)
水道法により、ビル、マンション、学校、病院などに設けられている給水施設で受水槽の有効容量の合計が10m3を超える施設は、一年に一回以上定期的に「国土交通大臣・環境大臣の登録を受けた検査機関」に依頼して、簡易専用水道の管理についての検査を受けなければなりません。(水道法第34条の2第2項)
当協会は、貯水槽水道における水道法第34条の2第2項の簡易専用水道の管理についての登録検査機関(国土交通大臣・環境大臣登録第21号) です。
検査を行う区域は埼玉県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、東京都(島しょ部を除く。)、神奈川県、新潟県(佐渡市及び岩船郡粟島浦村を除く。)、山梨県、長野県及び静岡県(熱海市の初島の区域を除く。)です。
"きれいな水、安心して飲める水に"
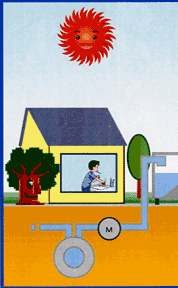
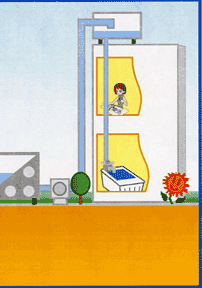
| 【現場検査】と【書類検査(建築物衛生法の適用を受ける施設)】の2つの検査があり、国土交通大臣・環境大臣登録検査機関が実施します。 |
|---|
現場検査1,施設の外観検査 設置者は、検査依頼書に必要事項を記入し、登録検査機関に提出してください。 |
書類検査 (建築物衛生法の適用を受ける施設)昭和62年4月1日から「提出書類検査」を受けることができるようになりました。 「提出書類検査」を受ける場合 |
【検査結果】検査終了後、検査結果報告書を交付します。 |
資料
・設置者へのご案内(しおり) 簡易専用水道設置者へのご案内(PDFファイル)
・現場検査「一般の施設」 検査依頼書(PDFファイル)
・書類検査「建築物衛生法 特定建築物の適用を受ける施設」
調査表(PDFファイル)
調査表記入例(PDFファイル)
■お問い合わせ・お申し込み先
電話またはメール news@saitama-kankyo.or.jp にてお問い合わせください。
上水道本部 水道検査課 電話:048-649-5115
■小規模貯水槽水道検査
平成15年4月1日から、受水槽の有効容量が10m3以下の小規模貯水槽水道についても、一年以内ごとに一回検査を受けるように努めることとされました。
※有効容量10m3を超える施設は、従来どおり一年に一回以上定期的に、必ず検査を受けることとなっています。詳細については「簡易専用水道検査」の項をご覧ください.
| 受水槽の有効容量が10m3以下の小規模貯水槽水道の検査です。 |
|---|
| 1.簡易専用水道管理検査に準じた検査 (1)施設の外観検査 受水槽、高置水槽及びその周辺の状況を検査します。 (2)水質検査 給水栓の水について、色、色度、濁度、臭気、味及び残留塩素の有無を検査します。 (3)書類の検査 衛生設備図面・水槽の清掃の記録等の有無を検査します。 |
| 2.給水栓の水質検査 給水栓の水について、色、色度、濁度、臭気、味及び残留塩素の有無を検査します。 |
| *「1.簡易専用水道管理検査に準じた検査」もしくは「2.給水栓の水質検査」のいずれかの検査が必要です。各市町村(条例)により検査内容が異なりますので、検査施設のある各市町村役場までお問い合わせください。 |
| 【検査方法と検査結果】 あらかじめ打ち合わせた日時に、当協会の検査員がお伺いして検査を行います。検査終了後に検査済証を貼付し、後日、検査報告書をお送りします。 |
■小規模貯水槽水道「Q&A」
Q.小規模貯水槽水道とはどのようなものですか?
A.市町村や水道企業団などの水道事業から受ける水のみを水源とし、その水をいったん受水槽に溜めた後、建物に飲み水として供給する施設で、受水槽の有効容量が10m3以下のものをいいます。
Q.貯水槽水道の衛生管理に対する規制はありますか?
A.受水槽の有効容量が10m3を超えるもの(簡易専用水道)については、水道法による規制となります。10m3以下のもの(小規模貯水槽水道)については、各自治体独自の条例による規制となります。
Q.受水槽の有効容量とはどういう意味ですか?
A.受水槽において適正に利用可能な容量であり、最高水位と最低水位との間に貯留される量をいいます。ただし、高置(高架)水槽の容量は含みません。
Q.小規模貯水槽水道検査とはどのようなことを検査しますか?
A.書類の保管状況、施設の状態と簡易の水質検査をあわせた管理状況の検査と、給水栓における5項目の水質検査の2種類がありますが、施設が設置されている各自治体の条例により検査内容が異なります。
Q.管理状況の検査の内容とはどのようなことを行なうのですか?
A.簡易専用水道と同じ検査内容を行います。
Q.検査機関にはどのようなところがありますか?
A.水道法第34条の登録機関等があります。詳しくは、各自治体にお問い合わせください。
Q.検査費用はどなたが負担するのですか?
A.施設の設置者、もしくは所有者です。
Q.管理状況の検査を受けるにあたって設置者が用意するものには
どのようなものがありますか?
A.
1)カギ(水槽の蓋、ポンプ室の入口、高置水槽がある場合は屋上出入口など)
2)図面(水槽の配置、給水する系統がわかるもの)
3)定期点検記録(清掃記録:受水槽、高置水槽等飲用の給水に必要なタンク類の清掃記録)
4)日常点検記録(水槽の周辺や内部を点検した記録及び給水栓の水を検査した記録)
Q.小規模貯水槽水道の検査は毎年やらなければいけないのですか?
A.1年以内ごとに1回行なうこととなっています。
■お問い合わせ
電話またはメール news@saitama-kankyo.or.jp にてお問い合わせください。
上水道本部 水道検査課 電話:048-649-5115
■浄化槽法定検査
「浄化槽法に基づく設置状況、維持管理状況の検査」(埼玉県知事指定)
当協会は、浄化槽の法定検査を行なう埼玉県知事指定検査機関です。
浄化槽法第57条第1項の浄化槽法指定検査機関(埼玉県知事指定指令環整第2107号)
埼玉県全域を二つの指定検査機関で実施しております。(検査担当地域図参照)
"快適な生活と美しい環境を目指して"
浄化槽の機能を十分に発揮させるために、正しい使用と保守点検・清掃(健康管理)及び法定検査(健康診断)が必要です。
保守点検・清掃、法定検査を受けるよう法律で義務づけられています。保守点検は「県知事登録を受けた業者」、清掃は「市町村長の許可を受けた業者」に委託してください。
法定検査は「県知事の指定を受けた公益法人」に依頼して、浄化槽の検査を受けなければなりません。(浄化槽法第7条、第11条) 参考:浄化槽法定検査リーフレット
【浄化槽法定検査詳細についてはこちら】 【浄化槽法定検査担当地域図】
浄化槽法定検査のお申込みについては、浄化槽検査課へご連絡いただくか、下記の申込みフォームより承っております。
■個人宅の浄化槽 法定検査のお申込み
浄化槽法定検査申込み(個人宅の浄化槽)
■事業所・アパート、貸家等のお申込み
浄化槽法定検査申込み(事業所・アパート・貸家等の浄化槽)
浄化槽法第7条検査の建築確認申請時窓口受付に関する「浄化槽法定検査依頼書(払込用紙)」の入手方法について
去る平成21年1月1日より、 「埼玉県浄化槽設置指導要綱」の改定により、 建築確認申請及び浄化槽設置届出書提出時に「浄化槽法第7条検査の依頼書の写し」を添付することとなりました。これに伴い、各方面から「浄化槽法定検査依頼書(払込用紙)」の入手を希望される方が増えております。
「浄化槽法定検査依頼書(払込用紙)」は当協会にて発行しており、入手希望者には郵送等にて対応しておりますので、浄化槽検査課宛にご連絡ください。折り返し、ご郵送いたします。
なお、直接手に入る場所はないか、という問い合わせが多くなっております。つきましては、大変お手数ではございますが、埼玉県内各環境管理事務所(北部・秩父以外)の窓口等に「浄化槽法定検査依頼書(払込用紙)」を置いて頂きましたので、急ぎの入手ご希望の方は各窓口でお受け取りくださるようお願いいたします。
■浄化槽一括契約制度について
【一括契約制度の目的】
浄化槽は、衛生的で快適な生活の基盤となる施設であるとともに、公共用水域の水環境の保全に大きな役割を果たす大変重要な施設です。
しかし、維持管理が適正に行われない場合には、浄化槽の正常な機能が発揮されず、悪臭や騒音、蚊・ハエの発生など、周辺の生活環境に悪影響を及ぼすだけでなく、身近な川や沼などの公共用水域の水質汚濁の原因にもなってしまいます。
このため浄化槽法では、浄化槽管理者(浄化槽を使用している方)に対して、
(1) 保守点検 : 装置の調整、消毒薬の補充
(2) 清掃 : 汚泥などの引き抜き
(3) 法定検査 : 機能診断、水質検査
の3つの維持管理を法律により義務付けています。
「浄化槽一括契約制度」とは、保守点検業者又は清掃業者が浄化槽を使用している方の窓口業者となり、(1)保守点検、(2)清掃、(3)法定検査の3つについて、一つの契約書で締結することです。
料金の支払先も窓口業者に一本化されますので、浄化槽を使用している方にとって、とても便利な制度です。
【一括契約のメリット】
1.煩雑な手続きから解放されます。
(1)保守点検、(2)清掃、(3)法定検査を別々にそれぞれの業者に委託(依頼)して、料金を支払っていた煩わしさが解放されます。
2.浄化槽の延命化につながります。
浄化槽が常に良好な状態となるよう、窓口業者(保守点検業者又は清掃業者)が(1)保守点検、(2)清掃、(3)法定検査の実施時期等を定めて、総合的に管理します。 浄化槽の状態について、契約に基づき保守点検業者、清掃業者、法定検査機関の3者間で共有化されますので、それぞれの業務に活かされるようになります。
その結果、浄化槽をより良い状態で長く使用できることにつながります。
【一括契約の申込方法】
埼玉県の当協会検査エリアでは下記の市町村において浄化槽一括契約がスタートしています。
平成28年7月1日~ 小川町
平成28年10月~ 滑川町
平成29年7月~ 朝霞市・新座市
平成29年11月~ 鴻巣市
平成30年11月~ 北本市
令和元年10月~ 坂戸市
令和元年11月~ 桶川市
令和2年10月~ 伊奈町
令和2年11月~ 上尾市
申込についてはご担当の維持管理業者(保守点検業者又は清掃業者)へお問い合わせください。
【一括契約のご案内】
・標準一括契約契約書(2020年10月版)(PDFファイル)
・標準一括契約契約書(2020年10月版)(wordファイル)
■お問い合わせ・お申し込み先
電話またはメール news@saitama-kankyo.or.jp にてお問い合わせください。
浄化槽本部 浄化槽管理課(土呂支所) 電話:048-778-8700
浄化槽本部 浄化槽検査課(西部支所) 電話:049-284-2911
■浄化槽法定検査新制度の導入
~平成23年10月1日より~ 埼玉県では、平成23年10月1日より浄化槽法第11条検査(定期水質検査)における合併処理浄化槽の放流水の水質検査項目にBOD測定を追加することになりました。また、平成31年4月より単独浄化槽にもBOD測定が追加されました。
BOD測定を導入することで、放流水質による浄化槽の機能判定を行うことができるとともに保守点検との区別を明確にすることが可能となります。
また、BOD検査の導入に併せて10人槽以下の浄化槽には、指定採水員制度を導入し11条検査実施率の向上及び浄化槽の適正な維持管理の推進を図ることになりました。
BOD(生物化学的酸素要求量)とは・・・
水中の有機物による汚濁の程度を示す指標で、有機物が微生物によって分解されるときに消費される酸素の量です。数値が低いほど有機物が少なく、汚れが少ないことを示します。
~ポイント~
1. 全ての浄化槽にBOD測定を追加
2. 10人槽以下の浄化槽ではBOD測定を追加したことにより 外観検査項目、水質検査項目、書類検査項目を一部軽減
3. 指定採水員制度の導入
■10人槽以下の浄化槽の検査は・・・
従来の11条検査は、浄化槽法定検査ガイドライン(外観検査75項目、水質検査4項目、書類検査6項目)で実施してきました。
水質検査にBOD測定を導入することにより、放流水質による浄化槽の機能判断が行うことが可能となりましたので、一部検査項目を軽減します。
○外観検査8項目
a. 漏水の状況
b. 浄化槽上部及び周辺の利用又は構造の状況
c. ばっ気装置の稼働状況
d. 流入管渠(路)の水流の状況
e. 放流管渠(路)の水流の状況
f. 沈殿槽の汚泥の堆積状況又はスカムの生成状況
g. 消毒剤の有無
h. 消毒設備の固定状況及び処理水と消毒剤の接触状況
・ 特記項目
(油脂類の流入状況、悪臭の発生状況、か、はえ等の発生状況など)
○水質検査項目3項目
a 透視度
b 残留塩素
c BOD
○書類検査項目4項目
a 保守点検の記録の有無
b 保守点検の回数
c 清掃の記録の有無
d 清掃の回数
■指定採水員制度とは・・・10人槽以下の浄化槽に適用
保守点検業の登録を受けている業者のうち、指定要件を満たした業者の浄化槽管理士であって、指定検査機関((一社)埼玉県環境検査研究協会および(一社)埼玉県浄化槽協会)の指定採水員指定講習会を受講し、指定検査機関が指定採水員として指定し、検査の補助業務を行います。
主な作業内容は、10人槽以下の浄化槽の検査項目に準じます。
※ただし、指定採水員が行った補助業務(外観検査項目、水質検査項目、書類検査項目)とBOD測定結果を基に、指定検査機関が総合的な判定を行います。
■指定採水員事業所一覧
指定採水員事業所一覧(PDFファイル)
■浄化槽水質検査指定計量証明事業所一覧
当協会では指定採水員制度の導入により、埼玉県環境計量協議会 様のご協力をいただき下記の計量証明事業所と委託契約を結んでいますので、BOD測定試料を搬入して下さい。
なお、当協会検査管轄のBOD測定試料は、直接当協会本部(さいたま市)及び西部支所(坂戸市)にて受付けることも可能です。
浄化槽水質検査指定計量証明事業所一覧(PDFファイル)
なお、10人槽以下の浄化槽の検査では、5年間に一度は指定検査機関による従来の浄化槽法定検査ガイドライン(外観検査75項目、水質検査4項目、書類検査6項目)+BOD測定を実施します。